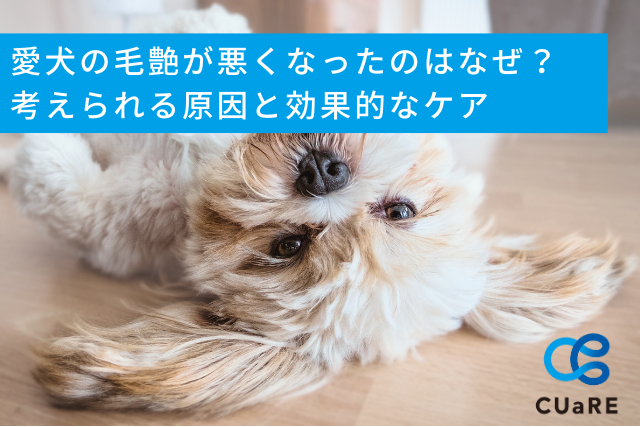
「最近、うちの子の毛がパサパサしてる…」
「毛艶が悪くなってきたような気がするんだけど、大丈夫かな?」
みなさんは愛犬の毛艶の変化に気づいて、心配になったことはありませんか?
実は、わんちゃんの毛艶は、見た目の問題だけでなく、健康状態を反映するものです。
愛犬が健康で、しっかりケアがされていれば毛艶はいいことが多い一方、毛艶に悪くなっている場合は、皮膚トラブルや病気のサインかもしれません。
今回は、毛艶が悪くなる原因、注意が必要なサイン、毛艶をよくするケアについて説明します。
毛艶が悪くなる原因

毛艶は、愛犬の全身の健康状態を映し出す鏡のような役割を果たしています。
もし毛艶が悪くなったと感じた場合、以下のようなことが起きているかもしれません。
- ・日常ケアの不足
皮膚トラブルなどを予防するうえで定期的にシャンプーなどのケアを行うことは重要ですが、これは毛艶においても同様です。
シャンプーやブラッシングを行わないと、被毛が絡まったり、汚れが溜まったりすることで毛艶が損なわれやすくなります。
- ・栄養不足や偏り
特定の栄養素が不足すると、被毛がパサパサしたり、毛艶が悪くなりやすいです。
毛艶はタンパク質やビタミン、必須脂肪酸などの栄養によって維持されるため、食事がおやつなどに偏ると毛艶に影響を及ぼすことが多いです。
- ・皮膚の炎症や感染
アレルギー、細菌感染、真菌感染などの皮膚トラブルは、毛艶を損なう大きな要因となります。
炎症があると皮脂の分泌バランスが崩れ、毛髪の保護機能が低下します。
- ・ホルモンバランスの乱れ
甲状腺機能低下症やクッシング症候群などのホルモンの病気は、被毛の変化や脱毛を引き起こすことがあります。
- ・慢性的なストレス
わんちゃんが長期的にストレスを感じると、免疫力が低下することで毛艶を悪化させる可能性があります。
- ・寄生虫感染
ノミやダニなどの外部寄生虫、あるいは内部寄生虫の感染は、栄養状態を悪化させ、毛艶に影響を与えることがあります。
- ・年齢による変化
年齢を重ねるごとに、わんちゃんもホルモンバランスの変化や代謝の低下が起こります。
その結果、被毛がパサついたり、毛艶が悪くなることがあります。
したがって、愛犬の毛艶は様々なことによって影響されます。
病気が原因となっている場合もあるため、愛犬の毛艶が悪くなった場合は獣医師に相談することが推奨されます。
特に注意が必要なサイン

毛艶の変化は、時として深刻な健康問題のサインである可能性があります。
毛艶が悪くなることに加え、下記のような症状が見られる場合は必ず獣医師に相談しましょう。
- ・急激な毛艶の低下
愛犬が突然毛艶を失ったりする場合は要注意です。
これはホルモンバランスの乱れなどのサインかもしれません。
特に、食事や環境に変化がないにもかかわらず毛艶が低下した場合は、獣医師による検査が望ましいでしょう。
- ・大量の抜け毛
換毛期のあるわんちゃんが季節の変わり目で毛が抜けることは自然ですが、いつもと比べて大量の抜け毛が出た場合や、部分的な脱毛が見られる場合はホルモンの異常、アレルギー、ストレスなどによって毛艶に影響が出ていると考えられます。
- ・皮膚の異常
皮膚が赤みを帯びていたり、フケがたくさん落ちる場合など、皮膚に異常がある場合はアレルギーや皮膚疾患、寄生虫による感染症が潜んでいる可能性があります。
- ・よく体をかく
頻繁に体を掻いたり、噛んだりする行動は、皮膚トラブルの兆候かもしれません。
アレルギー、ノミ・ダニ感染、真菌感染によってかゆみが引き起こされていると考えられます。
痒みが続くと皮膚を傷つけ、二次感染を引き起こす可能性があるため、早めの対処が必要です。
- ・食欲不振や元気の無さ
以前と比べて食欲が落ちていたり、全体的に元気がない場合、全身状態が悪化しているかもしれません。
内臓疾患や感染症などの病気が隠れている場合があるため、なるべく早めに獣医師に相談しましょう。
- ・しこりやできもの
皮膚にしこりやできものが見られた場合は要注意です。
良性の脂肪腫の場合もありますが、悪性の腫瘍の可能性もあるため放置するのは望ましくありません。
上記が見られる場合、毛艶の悪化だけではなく、より深刻な皮膚トラブルや病気の兆候である可能性があります。
心当たりがある場合は、獣医師に相談してケアを始めましょう。
毛艶を改善する日常ケア

毛艶が悪くなったらどうすればよいのでしょうか?
病気によって被毛に影響が出ている場合は根本的な治療も行う必要がありますが、ご自宅で行う日常ケアで改善がみられることも考えられます。
主な日常ケアとしては下記が挙げられます。
- ・適切なブラッシング
定期的なブラッシングは、きれいな毛艶を保つ上で最も重要なケアの一つです。
毛の流れにそって根元からやさしくブラッシングすることで、抜け毛を取り除いたり、毛が絡まりにくくなります。
望ましい頻度は頻度は毛の長さや量によって異なりますが、目安としてゴールデンレトリバーなどの長毛種は毎日、短毛種は週2〜3回ブラッシングを行うことが推奨されます。
- ・定期的なシャンプー
ブラッシングと同様、定期的なシャンプーは、わんちゃんの被毛と皮膚を清潔に保つために重要です。
一般的に1か月に1〜2回の頻度で行うことが望ましいとされています。
シャンプーをする際は、泡をしっかり洗い流したり、シャンプー後にしっかり乾かすことや保湿することを忘れずに行いましょう。
CUaRE BioMedical CARE SHAMPOOなど、保湿成分入りのシャンプーを使用することもおすすめです。
- ・バランスの取れた食事
前述の通り、健康な被毛を維持するためには、適切な栄養摂取が不可欠です。
良質なタンパク質、必須脂肪酸、ビタミン、ミネラルなどを摂取できるドッグフードを使用することが推奨されます。
また、獣医師にご相談の上で必要に応じてサプリメントを活用する選択肢もあります。
- ・ストレス管理
前述のとおり、ストレスは被毛や皮膚の状態にも影響を与えるため、ストレス管理は毛艶をよくすることに役立つといえます。
具体的には、散歩や遊びなどで適度な運動をしたり、部屋の温度と湿度を調整することで落ち着ける空間を作ったりすることがおすすめです。
このような日常ケアを実践することで、毛艶が改善されることが期待できます。
また、これらは皮膚トラブルや病気を予防することもあるため、愛犬の健康のためにも行って損はないでしょう。
獣医師によるケア

病気によって毛艶が損なわれている可能性がある場合は、獣医師によるケアが重要です。
下記を実践することで、適切な治療を行いましょう。
- ・健康診断
まず、健康診断を受ける習慣が大切です。
定期的に獣医師による健康チェックを行うことで、早期発見がしやすくなるため、毛艶の悪化を引き起こしている病気もより早い段階で治療を開始できることが期待されます。
頻度としては年1〜2回の定期健康診断が望ましいですが、それ以外でも愛犬に異常を感じたときもぜひ獣医師にご相談下さい。
- ・原因の特定
病気によって適切な治療法が異なるため、問診や検査を行うことで病気の有無や種類を確認します。
まず問診と視診を通じて、犬の全身状態や生活習慣、食事内容などを確認します。
これにより、毛艶の悪化が栄養不足やストレスといった生活によるものなのか、皮膚や内臓の疾患が関与しているのかを大まかに判断します。
次に、必要に応じて皮膚や被毛、血液やホルモンなどの詳細な検査を行います。
フケや脱毛が見られる場合は、皮膚を顕微鏡で観察して真菌や寄生虫の有無を確認したり、アレルギーが疑われる場合は、特定の食材を一定期間避ける食事療法などを実践します。
- ・治療の開始
治療は原因に応じて大きく異なります。
例えば、皮膚の感染症が確認された場合は内服薬や外用薬が処方され、寄生虫が原因なら駆虫薬が用いられます。
この際も定期的に獣医師による健康チェックを行い、症状の改善度合いを確認したり、治療法について相談することが重要です。
獣医師の診断に基づいて適切なケアを行うことで、毛艶の改善が期待できます。
まとめ
わんちゃんの毛艶の悪化には様々な要因があります。
愛犬に被毛のパサつきがみられる場合、それは日常習慣を見直す必要があったり、健康トラブルが起きていることを反映しているものかもしれません。
今回の記事の要点としては下記が挙げられます。
- ・毛艶は食事や皮膚疾患などによって影響される
- ・抜け毛や皮膚の異常など見られたら要注意
- ・シャンプーやブラッシング、食事などの日常ケアが重要
- ・病気が考えられる場合は獣医師による治療が推奨
毛艶は見た目だけでなく、健康とも関連するものです。
愛犬の健康を守るためにも、異常を感じた場合は獣医師にご相談ください。






